医師紹介

鹿野 晃 (かの あきら)
理事長・院長
経歴
- 藤田医科大学 医学部 卒業
- ペンシルバニア大学 医学部 留学
- アイオワ大学 医学部 留学
- 青梅市立総合病院 救命救急センター 医長
- 遠山脳神経外科 副院長
- 医療法人社団 晃悠会設立 理事長就任
- 医療法人社団 晃悠会 ふじみの救急クリニック
院長就任(遠山脳神経外科:継承) - 医療法人社団 晃悠会 ふじみの救急病院 院長
資格
- 日本救急医学会 救急科専門医
- 日本脳神経外科学会 会員
- ICLS(二次救命処置)コースディレクター
- JATEC(外傷初期診療)プロバイダー
- JPTEC(病院前外傷初期診療)プロバイダー
- ISLS(脳卒中初期診療)プロバイダー
- PALS(小児二次救命処置)プロバイダー
- 日本DMAT(災害派遣医療チーム)隊員
- 埼玉地域DMAT隊員
- 陸上自衛隊 予備自衛官 医官(二佐)
- 民間救命士統括体制認定機構 民間メディカルコントロール医師
- 東京消防庁 救急隊指導医(元)
受賞
- 埼玉県知事表彰(救急医療功労医療機関)
- 埼玉県医師会表彰
- 日本旅行業協会(JATA) 企画創造部門 グランプリ(ふじみの救急病院 検査してGoTo社員旅行!!)
- 千里メディカルラリー(救命救急の全国大会) 7位

遠山 隆 (とおやま たかし)
脳神経外科 部長
経歴
- 東京医科大学 医学部 卒業
- 東京女子医科大学 大学院
- 日本医科大学 大学院
- ペンシルバニア大学 医学部 留学
- 三芳厚生病院(現イムス三芳総合病院) 脳神経外科 部長
- 遠山脳神経外科 院長
資格
- 日本脳神経外科学会 脳神経外科専門医
- 認知症サポート医
- 医学博士

佐藤 孝宏(さとう たかひろ)
循環器内科 医長
経歴
- 札幌医科大学 医学部 卒業
- 札幌医科大学付属病院 第二内科
- 旭川赤十字病院 循環器内科 腎臓内科
- 埼玉石心会病院 循環器内科
資格
- 日本心血管インターベンション治療学会専門医
- 日本循環器学会認定専門医
- 日本内科学会認定総合内科専門医
- 医学博士

金 泰秀(きむ てす)
救急科 医長
経歴
- 聖マリアンナ医科大学 医学部 卒業
- さいたま赤十字病院 救命救急センター
- 公立豊岡病院 救急部
資格
- 日本救急医学会 救急科専門医
- ICLS(二次救命処置)プロバイダー
- JATEC(外傷初期診療)プロバイダー
- JPTEC(病院前外傷初期診療)プロバイダー
- ISLS(脳卒中初期診療)プロバイダー
- PALS(小児二次救命処置)プロバイダー
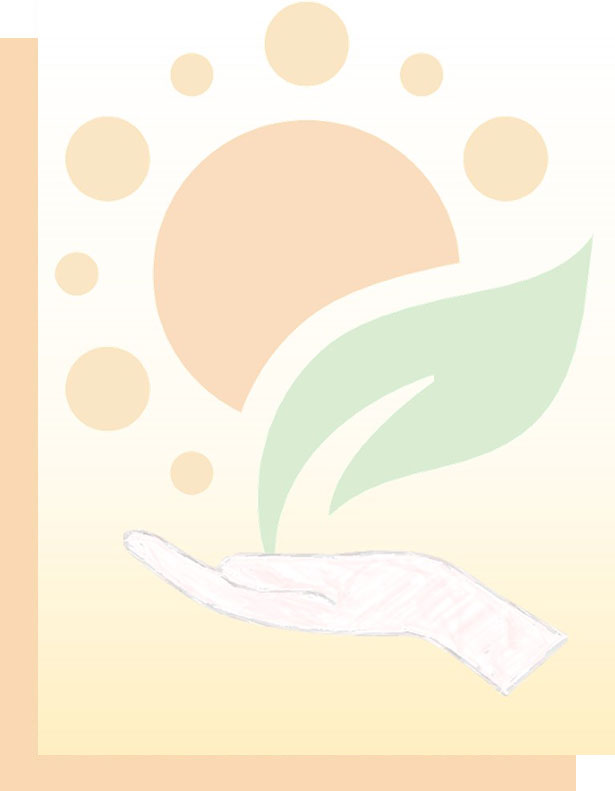
湯淺 翔(ゆあさ しょう)
循環器内科
内科
経歴
- 新潟大学 医学部 卒業
- 立川綜合病院 循環器内科
- マドリードサンカルロス病院 留学
資格
- 日本循環器学会認定専門医
- 日本心血管インターベンション治療学会認定医
- 日本内科学会認定内科医
- ICLS(二次救命処置)プロバイダー
- JATEC(外傷初期診療)プロバイダー

後藤 園香(ごとう そのか)
訪問診療科
内科
循環器内科
経歴
- 東京女子医科大学 医学部 卒業
- 戸田中央総合病院 初期研修・心臓血管センター内科
- マドリード サンカルロス病院 留学
- 立川綜合病院 循環器内科
資格
- 日本循環器学会認定専門医
- 内科認定医
- 日本医師会認定産業医
- 日本医師会認定健康スポーツ医
- SHD心エコー図認証医
- 日本周術期経食道心エコー認定医
- 緩和ケア研修会修了医師

長田 直也(おさだ なおや)
放射線科
経歴
- 大分大学 医学部 卒業
- 千葉県立病院群
- 千葉県がんセンター
資格
- 日本医学放射線学会 放射線診断専門医

阿部 愛(あべ あい)
救急科 専攻医
経歴
- 旭川医科大学 医学部 卒業
- 旭川医科大学病院
- 北見赤十字病院
非常勤医師
神山 信也
埼玉医科大学 脳神経外科 教授
埼玉医科大学 国際医療センター 脳血管内治療科 診療部長
専門分野
脳血管内治療全般、脳卒中治療全般
主な資格
- 日本脳神経血管内治療学会専門医・指導医
- 日本脳神経外科学会専門医・指導医
中埜 信太郎
埼玉医大 国際医療センター 心臓内科 教授
専門分野
- 循環器病学一般
- 虚血性心疾患
- カテーテルインターベンション
- 救急一般
- 小児科
主な資格
- 日本内科学会認定内科医
- 日本循環器学会専門医
- 日本心血管インターベンション治療学会認定医
- 日本小児科学会専門医
- 日本救急医学会専門医
梶本 隆太
埼玉医科大学国際医療センター 脳血管内治療科
専門分野
- 脳血管治療・脳卒中治療全般
主な資格
- 医学博士
- 日本脳神経外科学会 専門医
- 日本脳卒中学会 専門医
- 日本脳神経血管内治療学会 専門医
谷口 尭彦
埼玉医科大学国際医療センター 脳血管内治療科
専門分野
- 脳血管治療・脳卒中治療全般
主な資格
- 日本脳神経外科学会 専門医
- 日本脳神経血管内治療学会 専門医
吉田 馨次朗
埼玉医科大学国際医療センター 脳血管内治療科
専門分野
- 脳血管障害の外科治療
主な資格
- BLS、ALS講習修了
戸村 哲
防衛医科大学校 防衛医学研究センター教授
専門分野
外傷研究部門、脳神経外科(神経外傷、脳神経外科救急)
主な資格
- 医学博士
- 日本脳神経外科学会専門医・指導医
- 日本脳神経外傷学会学術評議員・認定指導医
- 頭部外傷ガイドライン作成委員
- 頭部外傷データバンク検討委員
- 日本脳神経モニタリング学会評議員
- 日本脳神経外科救急学会評議員・PNLSインストラクター
- JATECプロバイダー
南里 和紀
東京医科大学 八王子医療センター脳神経内科 兼任教授
経歴
- 東京医科大学 卒業
- 東京医科大学第三内科
- フランス国立科学研究センター脳血管研究所 留学
- 東京医科大学八王子医療センター
- 東京医科大学脳神経内科 教授
専門分野
神経内科
主な資格
- 医学博士
- 日本認知症学会専門医・指導医
- 日本内科学会認定医・総合内科専門医
- 日本神経学会専門医・指導医
- 日本脳卒中学会評議員
- 日本神経治療学会評議員
- 日本神経感染症学会評議員
- 日本小脳学会評議員
片栁 直子
経歴
- 東邦大学医学部卒業
- 東邦大学医学部大学院卒業
- 東京都立駒込病院 内分泌代謝科 部長
専門分野
糖尿病内科
主な資格
- 糖尿病内科専門医
スタッフ紹介

板垣 光純
副院長/看護部長
看護師になり20年が経ちました。
これまでは地域の急性期病院に勤めて参りましたが、常に、‟もう少し早く誰か気が付かなかったのか?”、‟相談出来る人はいなかったのか?”などの想いを強く持っていました。
救命の連鎖とはまず「予防」から始まります。病院に入院した時は既に遅いのです。
動けなくなった状態を延ばすのでは無く、健康である時期を出来るだけ延ばす。
健康寿命を延ばす!その実現の為にこの病院に入職しました。
これまでの経験を活かし、緊急を要する疾患には迅速・適切に対応します。
加えて、気軽に相談できる町の保健室の様な身近な存在を看護部は目指します。
健康や介護の問題など是非気軽にお声を掛けて下さい。
またEMT科(救急救命士)と連携し救急車の運用も始まりました。
必要としている人へ医師・看護師が同乗し駆け付けます。
この病院は救急のプロを育成します。

松本 高宏
主任
看護部では、当院が「皆が気軽に受診ができて、何回でも繰り返し受診したいと思える病院」であるよう心がけています。
小さいお子様からご高齢者まで、健康に不安を覚えたり急な症状でお困りのとき、土日・夜間を含めて受診・相談ができる体制を整えています。
日常生活でちょっと体調が悪いなと思ったとき、「こんなことで受診してもいいのかな」、「先生に怒られたりしないかな…」そう思われることはありませんか?
実際に当院で受診される患者様からそういったお声を頂くことがあります。
ですが、本当はそういったときが一番の受診のきっかけですので、ぜひ受診してみてください。
もし、受診で迷ったときや診察のときに言い出しにくいこと、お困りのことがありましたら看護師へお気軽にご相談いただけたらと思います。

竹内 昇史
主任
放射線技師4名で2台のMRI・CT・レントゲンを駆使し、24時間365日検査に対応しております。c
迅速に的確な情報を伝え、医師の診断・治療のサポートが出来るよう日々研鑽を積んでおります。
最新鋭MRIは急性期脳梗塞や動脈瘤検出に特に優れた威力を発揮し、所要時間も約10分と短く患者様をお待たせ致しません。
物忘れにはVSRAD解析という海馬の萎縮を数字化できる検査も行っており患者様には大変ご好評頂いております。
狭いところが苦手の患者様でも安心して検査が受けられるよう、オープン型のMRIもあり、整形外科や婦人科系の疾患を中心に検査を行っております。
CT検査では体のあらゆる場所を細かく輪切りにして撮影することができ、造影剤を使った検査も行っております。
画像診断の専門医師による遠隔読影にも対応し診断精度の向上を図っております。
放射線検査に関する不安や分からないことがございましたらお気軽にご相談下さい。
医師・スタッフについて
ふじみの救急病院では医師・スタッフが、患者さんに適切な診療・処置、ご説明ができるよう、定期的に勉強会を行っています。
